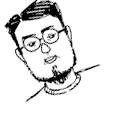WebでFIGletなんて使うところないよなあ、と思ってたら。
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<!--
88 88
,d 88 88
88 88 88
MM88MMM 88 88 88,dPYba,,adPYba, 88,dPPYba, 88 8b,dPPYba,
88 88 88 88P' "88" "8a 88P' "8a 88 88P' "Y8
88 88 88 88 88 88 88 d8 88 88
88, "8a, ,a88 88 88 88 88b, ,a8" 88 88
"Y888 `"YbbdP'Y8 88 88 88 8Y"Ybbd8"' 88 88
-->
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">TumblrのソースにはFIGletが!