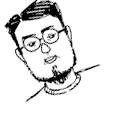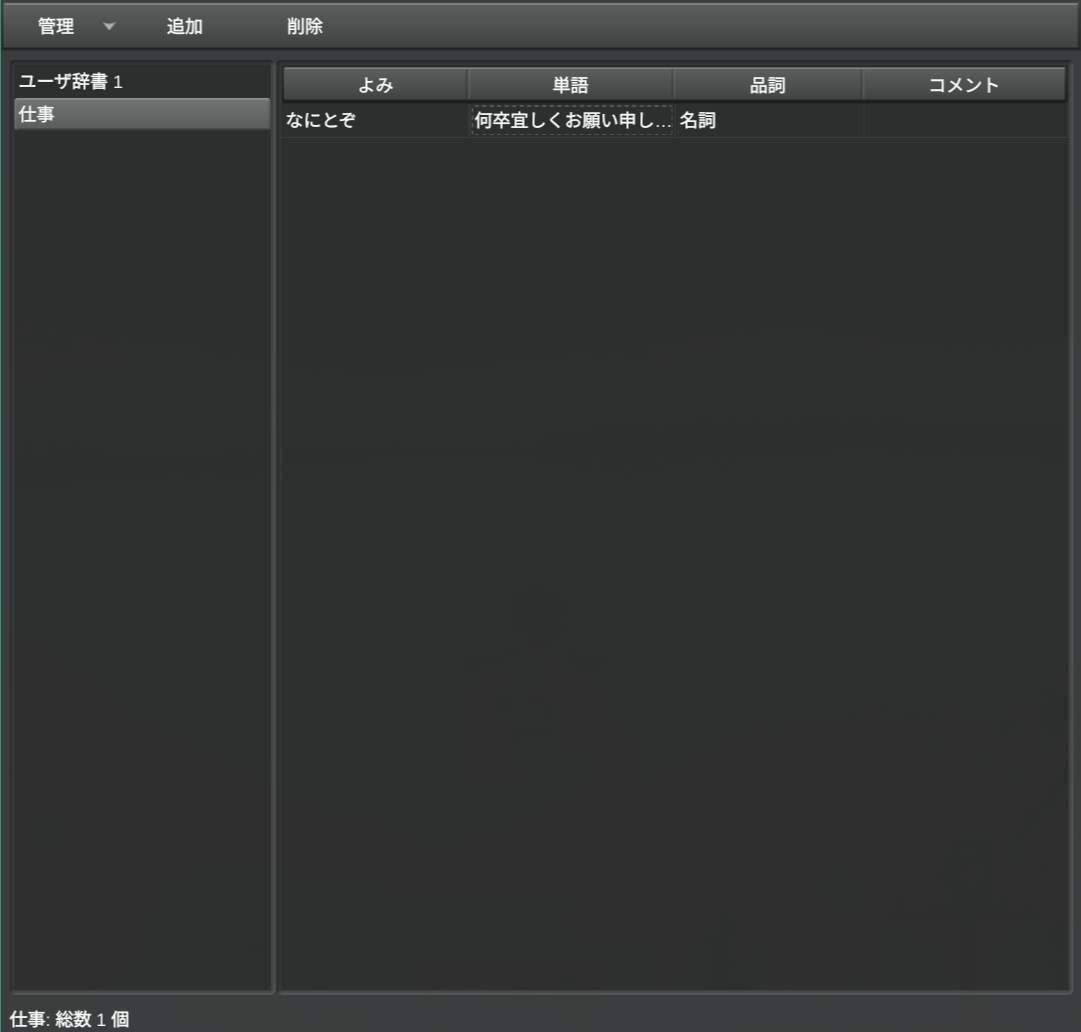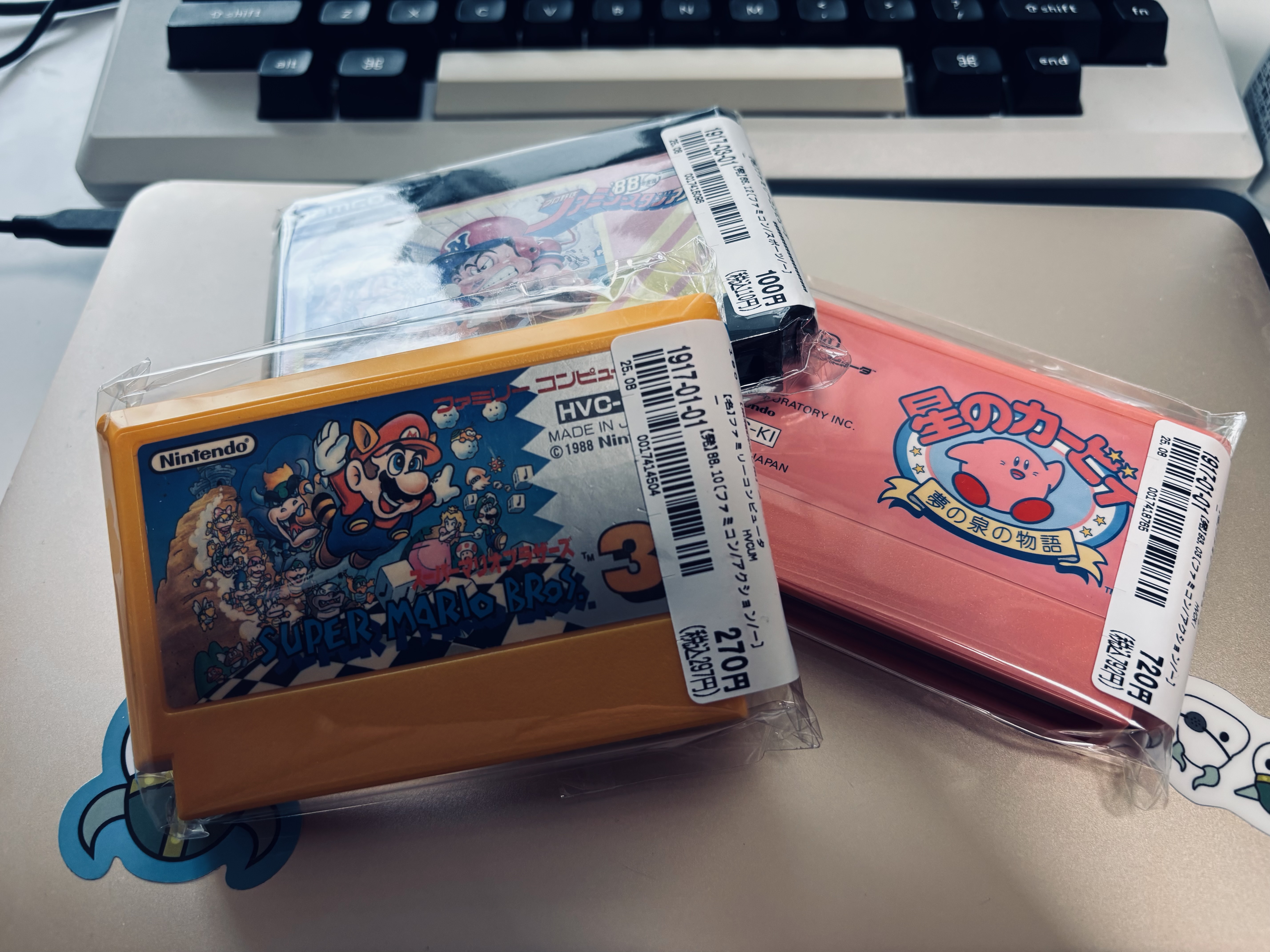フィヨルドブートキャンプというプログラミングスクールをやっているわけですが、今はAIが話題で、プログラマーとしての就職に興味がある人にとっては、
「これからどうなるんだろう?AIによってプログラマーが不要になる?」
というのが心配なんじゃないかなと思います。
プログラマーは不要?
正直、誰もわからないんですが、最近やっとAIが何をやってくれるのかについてみんなの期待と実情が落ち着いてきた感はあります。
「AI時代にプログラミングを学ぶ必要があるのか?」
についての答えは、
「人間がAIの書いたコードを理解する必要があるか?」
にかかっていると思います。
プロトタイプとかではないプロダクションレベルでは理解している必要があって、これはしばらく続きそうです。
弊社でやってるエンジニア紹介に関しても「プログラマー採用したい」という会社さんの需要は全く減ってないです。
まあ、なので安心してプログラマーになってほしいなと思うんですが、それとは別に、現在既にプログラマーな人がAIどんな感じなのかを伝えたい。
今最高に面白い
正直、AIがあることで、
「やろうと思えばできるけどクソ面倒だからやりたくなかったこと」
とか、
「そもそも不可能かもしれない壮大な計画や超マニアックなプロジェクトに面白半分でとりかかる」
というのもできて超楽しい。
もちろん、ライブラリのコードを自分でカッチリ書くというようなコーディングの楽しみも失われてないし、プログラマーの情緒的には、
「ダリィことはAIに任せて自分は楽しいところどりできて最高」
という感じ。
また、Webサービス屋としても、
今まで「解決したいけど不可能だった問題」がAIで解決できるようになって、Webサービスとして解決できる問題の幅が超広がって楽しい。
ジョブセキュリティーとかキャリアプランとかどーでもよくなるぐらい面白い。
まとめ
ようするに今までと同じだけど、
「おれもやるからきみもやれ」
ということ。